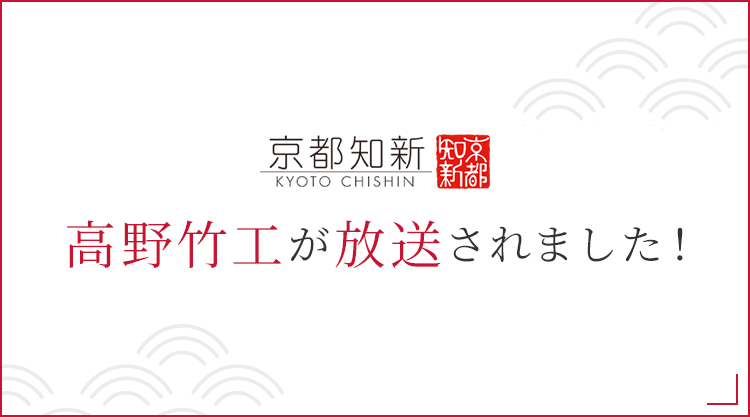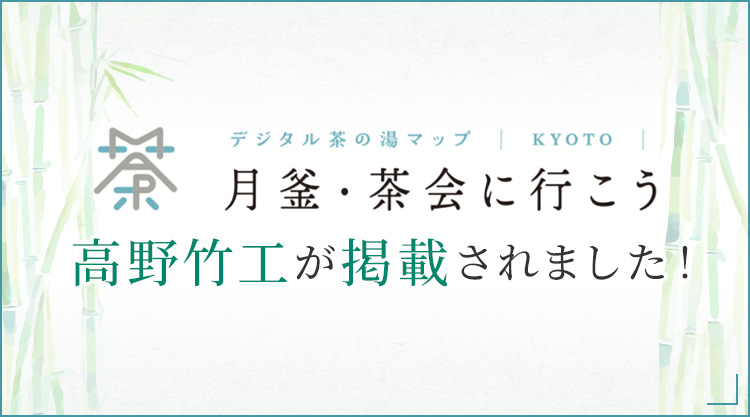孟宗竹の伐竹作業が始まると同時進行で伐った竹を油抜きしていきます油抜きを終えた竹は天日に晒して1週間ほどコロコロ回せば美しい白竹色に変わる・・・はずなのですが台風16号の雨がしばらく続くとほんの少し色の変化がゆっくりになりますしかし油抜きの作業は止められません次々と仕上がる青竹とともに秋晴れの空を待つ
競争から始まり相互理解そして相互扶助へ
2016.9.17 竹林便り
本格的な伐竹の季節休息のひとときがかけがえのない時間に感じますお布団の洗濯に行ったクリーニング店で12年前に買った懐かしい1冊を久しぶりに読み返しましたご著書を書かれた鬼塚英昭氏は大分県別府市の竹細工を家業とする家の生まれ平成15年12月20日発行までに約9か月間大分県の全市町村を巡って参考文献を集めそれだけではなく何より心を打たれるのは大分県一円の山深い田舎へ主に青竹で篭を編む職人と竹切り子を自...
夏の青空がいく日も続きようやく降った29日の雨は命を吹き返すほどのありがたい雨でした竹に住む3寸のお姫様も心地良い雨音を聞きながら駆け回って喜んでいたかもしれません月が美しくなる季節の始まり
ヒマワリのような笑顔の庭掃除のおっちゃんと垣根をいじりながら話したこと・・・「あれかな・・・庭から出る木や竹は燃やす以外になんか処理の方法はないものかな?」竹や木から人の生活が離れましたから大きな課題になっていますね(R)「数十年前までお風呂なんか薪で炊いてたよ」そんなふうに何かに活かせたらいいですよねバイオエタノールとか電気に変えて売れたらいいですよね(R)「設備投資が大変やな(笑)」それでも沢...
雨の降らない連日の猛暑の中今年の伐竹作業が始まりましたさすがにこの時期は時々一呼吸を入れないとふっと目が回りそうになることがありますそんな時に吹く山からの涼しい風には本当に生きる力をもらいますギリギリの厳しい自然を生きる生き物の姿に一流のアスリート魂を垣間見る
照りつける真夏の太陽を柔らかな木漏れ日に変える自然のサンシェードひと雨降った後に吹いてくる風はこの上なく気持ちいい夏の仕事帰りの夕焼けの空はどこか優しく心を癒してくれる
7月18日近畿地方の梅雨明けとともにセミの大合唱が響き渡り保津峡からの川風を感じながら自転車をこいでいると風変わりな竹を発見しました長い!節間が60センチくらいあります「トウチク(唐竹)だな・・・」観賞用として庭木などによく植えられているため名前はすぐに分かったのですがなんとも悩ましいのはこの竹のもつ別名の「ダイミョウチク(大名竹)」少なくともRさんの調べた範囲ではこのトウチクの他にナリヒラダケ・...
不思議な物体・2016
2016.7.14 竹林便り
7月は竹林の中の命の営みが一年中でもっとも感じられる月〝巣立ち”の季節でもあります鳥や虫たちも姿かたちは一人前でもなんとなく動きがかわいらしく好奇心でワクワクしているのが伝わってきます作業中のRさんの目にふと何かが見えました綿かな・・・?わわっ動いたぞ足が6本見えるけれどどっちが頭なんだろ…とんがった方をフリフリしながら歩くんだな…家へ戻って調べてみるとどうやらアオバハゴロモの幼虫らしい成虫になる...
毎年新しい地下茎を見つけると記録をとっているのですが今年の地下茎1号の発見は6月9日とかつてない早い発見でしたタケノコはまだ皮に包まれていますそれもそのはずそれは近頃毎朝のようにこの竹林へやって来ているイノシシが掘ったものでした若い地下茎から出る根は桃色なので一目で分かります弊社の管理竹林の中で唯一「裏年」なこの林食べるタケノコがなくなりついに地下茎を食べ始めたか・・・でも大丈夫!心の内でイノシシ...
昨年の7月初め頃一部の竹林で赤団子とスス病が発生しましたいくつか資料を当たってみると赤団子は密集してきたサインでさほど問題はなさそうでしたしかしスス病の方が・・・資料内容には新しい稈や葉がススで覆われたようになる。通常はアブラムシやカイガラムシが共生するようで、彼らの排出物に病原菌が付着する。葉の表面にススが多数付けば炭酸同化作用(光合成)を妨げる。とあります若い笹葉や竹に菌がついてしまうとはこれ...