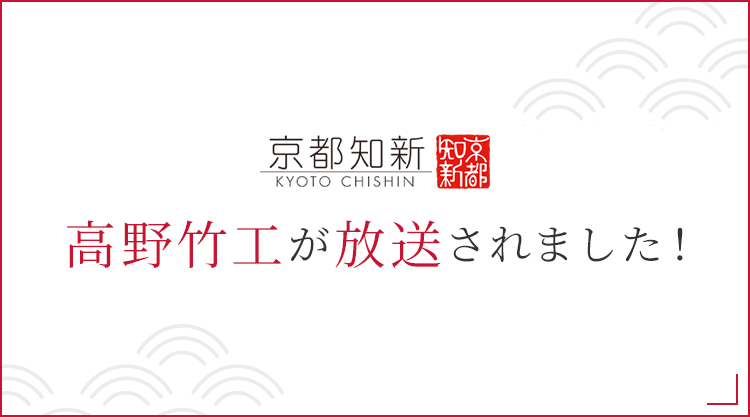竹林(マタケ)を整備する、或いは持続的に管理する時
①【目的】その竹林が果たしている役割は何か
(景観保全林・筍生産林・竹材生産林・防災多機能林など)
②【目標】目的を達成するための項目
③【課題】項目の内、まず実行できることは何か
④【要点】課題達成の実践ポイント
を考える。
20年間伐り子に携わり、マタケの竹材生産林と景観保全林・防災多機能林が同時に成立する
ように感じており、そのための実践ポイントを観察記録としてまとめておきたい。
前置きとして、九州や京都で古くから行われている「新竹残し法(仮名)」も
理にかなった竹林の管理方法であり、状況に応じて活用されることを願うものである。
②【目標】マタケの竹材生産林・景観保全林・防災多機能林を達成するための項目
◇枯れ竹、風倒竹、病気竹、イモ竹の整理伐➡土へ還す方向
テングス病、風倒竹は虫が入っていなければ利用可能
◇稈齢10年以上の竹の伐竹(稈齢=樹齢択伐という)➡利用可
ここまでで竹の伐採はほぼ完了し、1~2年に一度一気に実行しても良いし、
まめに実行しても良い。竹と竹の間隔や、何本残すか、などは考えない。
◆道づくり➡人が歩く場所を決めることでタケノコや地下茎の若い芽を傷めない。幅は細くて良い。
また経験から、林内に空間を作ると景観が美しくなる。チップ材があれば撒くと良い。
林道の両側5メートル程度を美しく整える。枯れ竹の棚積み、竹の枝、持ち込みの落ち葉などは奥の方へ
整然と置くと景観を損なわない。肥料過多とならない程度。
◆イノシシ対策➡マタケの地下茎や虫が好物。一度入られると止められないため初期に対策が必要。
電気柵は景観を損なうため、強固な土台を築き竹をはめ込む方法が長期で見ると良いかもしれない。
有効策として水路、高低差、生け垣、竹垣など合わせて行うと良い。
◆竹林の周囲を樹木で囲む。特に南側、東側➡樹皮を持たない竹は日焼けに弱い。また竹林周囲の風倒竹を木が防ぐ。
台風などで倒れた際の、隣家への被害想定も必要。