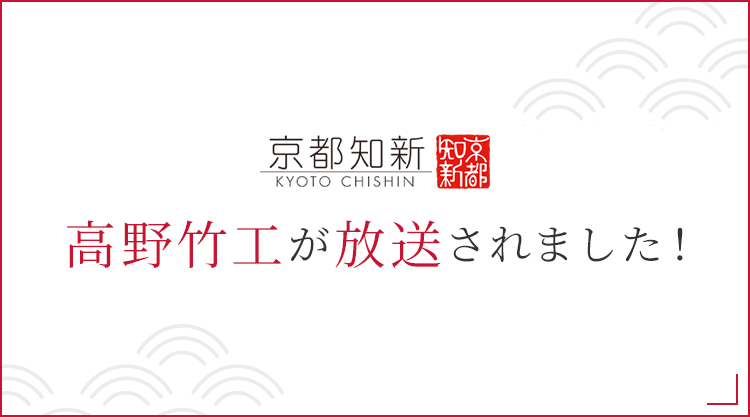先日 個人的に「生活と化学」について 勉強する機会がありました
化学の歴史に始まり 東日本大震災の原発の放射能汚染まで
内容が多岐に富み 興味深く学びました
試験問題の最後に "本講義で学び印象に残ったことなどを今後の展開も含め簡潔に述べよ" とあり
暫し 「化学と竹」というテーマで考えてみることにしました
”化学と竹”
竹に携わる仕事をしていると、プラスチックは竹産業を衰退させたと耳にすることがある。しかし講義を通して今、私の考えは少し変化してきている。
戦後、多くの起業家や研究者が竹の持つ特性に可能性を感じて、工業的利用を目指した。もしも成功していたならば、代替製品にも負けず新たな活路として生活を潤し、美しい竹林が人々の涵養の場となっていたかもしれない。
しかし現実には、多くのそれらは継続しなかった。木とは異なる竹の特性を理解しないまま始動した試みは、結果的に竹林乱伐となり原料調達に行き詰まり、他の諸要因も重なり頓挫した。私はそのように考えている。
製品開発において優れた成果が出ているものも多くあっただけに、惜しいものである。
確かに竹はプラスチックに取って代われた。しかしながら化学においては竹で成果を出したのである。
そうして今、人々は竹に目を向けなくなった。同時に山も荒廃し、シシ対策の講じられなくなった境界からは思うままにイノシシが好物のマタケの根を掘りに人里に降りて来る。生命力の強い竹はぐんぐんと山頂に地下茎を伸ばし、生態系の破壊者と言われるまでになってしまった。
話しは変わり、私が生まれる100年ほど前、アメリカの発明家トーマス・アルバ・エジソンは日本産の竹のフィラメントで白熱電燈を発明した。転機というものは、ある日突然にやってくる。その時に私たちは、再び竹林という大きな可能性に立ち向かうことになる。もしもその高いハードルを越えられた時こそは、化学は竹を救うことになるかもしれない。そして竹が再び社会を潤す。そう私は信じている。